郵便物を送る際、封筒やはがきに切手を貼るのは基本的な作業です。
しかし、いざ貼ろうとしたときに 「切手を貼るスペースがない!」 という経験をしたことはありませんか?
- 住所や名前を大きく書きすぎてしまった
- イラスト入りのはがきで切手を貼る場所が見つからない
- 特殊なサイズの封筒を使っていて貼る位置に迷う
こうした状況では、誤った場所に切手を貼ってしまうと、郵便物が正しく処理されずに配達が遅れる可能性があります。
場合によっては、郵便局から差し戻されてしまうことも…。
本記事では、
✅ 切手を貼る基本的なルール
✅ 貼るスペースがない場合の対処法
✅ 切手を正しく貼るためのポイント
を詳しく解説していきます。
「切手を貼る場所がない…どうしよう?」と困ったときに、この記事を読めば 正しい解決策が見つかる はずです。
切手を貼る基本的な位置とその理由
郵便物に切手を貼る際、 「どこに貼るべきか?」 というルールが決まっています。
適切な位置に貼らないと、郵便局の機械で処理できず、配達が遅れたり戻ってきたりする可能性があります。
ここでは、 切手を貼る基本的な位置 と その理由 について詳しく解説します。
封筒、はがきの切手の正しい位置
郵便切手は郵便物の表面の左上部(横に長いものは、右上部)に貼ることになっています。
封筒やはがきには 「縦書き」 と 「横書き」 の2種類があります。
それぞれの書き方によって、切手を貼るべき位置は以下の通りです。
📌 縦書き(縦に長いもの)の場合の切手の配置
➡ 左上 に切手を貼る
📌 横書き(横に長いもの)の切手の配置
➡ 右上に貼る
📢 注意点
✅ 切手は まっすぐ 貼ること(斜めになっていると機械が認識しづらい)
✅ 貼る位置に 折り目やシワがないこと(破損すると無効になる場合も)
✅ 原則的に封筒の裏側に貼らないこと(裏側に貼る場合はルールあり、後述)
✅ はがきには 切手を貼るスペースがあらかじめ印刷されていることが多い 、その場合は、 印刷された枠内に貼ればOK
なぜ切手を左上(右上)に貼るのか?
切手の位置には 郵便局の処理システム が関係しています。
郵便局では、普通郵便の消印処理を自動化するため、郵便物をすべて縦向きに整えて機械に通します。
この機械は、縦書き封筒を基準に設計されており、決められた位置に消印を押すようプログラムされています。
横書き封筒の場合でも、正しく処理されるよう切手は右上に貼る必要があります。
もし左上に貼ってしまうと、機械で縦向きに並べた際に切手の位置が下側になり、適切に消印を押せなくなってしまいます。
そのため、ルール通りの位置に貼ることが重要です。
切手の貼り位置を間違えたらどうなる?
切手を誤った位置に貼ってしまった場合、郵便局の処理に影響が出ることがあります。
✔ 機械が切手を認識できず、手作業で処理される
✔ 処理に時間がかかり、配達が遅れる可能性がある
✔ 場合によっては差し戻されることもある(特に海外郵便)
もし 切手を間違えて貼った場合 は、 剥がして貼り直すか、新しい封筒・はがきを使う のが安全です。
切手を貼るスペースがない場合の具体的な対処法
郵便物を送る際、 「切手を貼るスペースがない!」 という状況に直面することがあります。
例えば、こんなケースが考えられます。
✅ 宛名や住所を大きく書きすぎた
✅ デザイン性の高いはがきで、切手を貼る余白がない
✅ 複数の切手を貼る必要があり、スペースが足りない
✅ 封筒のサイズが小さく、貼る場所が限られている
このような場合でも、適切な方法で対応すれば問題なく郵便物を送ることができます。
ここでは、 切手を貼るスペースがない場合の具体的な対処法 を紹介します。
1. 住所や宛名のレイアウトを工夫する
はがきや封筒の 書き方のバランスを見直す ことで、切手を貼るスペースを確保できることがあります。
📌 対策方法
✔ 宛名や住所を小さめに書く(極端に大きな字は避ける)
✔ 中央寄りに書かず、適切な余白を確保する
✔ 印刷する場合は、フォントサイズを調整する
💡 ポイント
- 文字サイズを小さくしすぎると、 読みにくくなってしまうため注意
- 切手を貼るために、 無理に宛名の配置を崩さないようにする
2. 切手を縦に並べて貼る
複数の切手を貼る必要がある場合、 横に並べるとスペースを取ってしまう ことがあります。
この場合、 切手を縦に並べる ことでスペースを確保できることが多いです。
📌 対策方法
✔ 切手を縦に並べる(封筒の端に沿うように)
✔ 小さい額面の切手を選ぶ(1枚のサイズが小さいものを使う)
💡 ポイント
- 切手は 上下をそろえて綺麗に貼る
- 極端に小さな切手を何枚も貼るのは 見た目が悪くなる ので、適度なサイズを選ぶ
3. 切手を封筒の裏面に貼る(例外的な方法)
通常、 切手は封筒の表面に貼る のがルールですが、どうしてもスペースがない場合は 裏面に貼る ことも可能です。
切手裏面貼付の方法と注意点
この方法は 郵便局の判断 によって対応が異なるため、 ルールを理解し、適切な手順で行う ことが重要です。
1. 切手の裏面貼付とは?
以下のような理由で 表面に貼れない場合 に限り、封筒の裏面に切手を貼ることが認められることがあります。
📌 裏面に貼るケースの例
✅ 表面に宛名や差出人の情報が多く、切手を貼るスペースがない
✅ デザイン性の高い封筒やはがきで、指定の切手スペースがない
✅ 複数の切手を貼る必要があり、表面では収まらない
💡 重要ポイント
- すべての郵便物で裏面貼付が認められるわけではない
- 郵便局の窓口で事前確認をするのがベスト
- 郵便物によっては、裏面貼付では受付不可になることもある
2. 切手を裏面に貼る際の手順
封筒やはがきの裏面に切手を貼る場合、以下の 3つのポイント を守ることが重要です。
📌 ステップ 1:裏面の適切な位置に貼る
- 封筒の 左上または右上 に貼る(中央や下側には貼らない)
📌 ステップ 2:郵便局の窓口で確認する
- ポスト投函ではなく、郵便局の窓口で直接差し出す
- 窓口で「切手を裏面に貼っていますが、問題ありませんか?」と確認する
📌 ステップ 3:必要に応じて手書きで「切手裏面貼付」と記入
- 郵便局員から指示があった場合、封筒の表面(宛名の横)に「切手裏面貼付」と手書きで記入する
- 記入が不要な場合もあるが、記入しておくと確実
3. 切手を裏面に貼る際の注意点
❌ 注意点 1:ポスト投函しない
切手を裏面に貼った郵便物は、ポスト投函すると処理できず返送される可能性がある。
➡ 必ず郵便局の窓口で受付すること!
❌ 注意点 2:封筒の中央や下部に貼らない
切手は 裏面の左上または右上に貼るのが基本。
中央や下部に貼ると、郵便局の機械が認識できずトラブルの原因になる。
❌ 注意点 3:糊付けやテープの使用はNG
切手が剥がれるのを防ぐために、 糊やテープで補強すると無効になる可能性がある。
➡ しっかり貼り付けるが、余計な加工はしないのがベスト
4. 切手を重ねて貼る(慎重に!)
どうしてもスペースが足りない場合、 切手を少し重ねて貼る という方法もあります。
📌 対策方法
✔ 上下または左右の一部を少し重ねて貼る
✔ 切手の額面やデザインが隠れないように調整する
💡 注意点!
- 切手の金額(額面)が隠れないようにすること!
- 消印が押せるように、なるべくずらして重ねるのがコツ
- 局員に確認すると確実
5. 料金別納郵便を利用する(大量発送向け)
個人での利用は少ないですが、 企業や団体向け には 「料金別納郵便」 という方法があります。
📌 対策方法
✔ 郵便局の窓口で「料金別納」を依頼する
✔ 切手を貼らずに発送できる(一定枚数以上の郵便物が対象)
💡 ポイント
- 一般の個人利用には向いていないが、 大量の郵便物を送るときに便利
- 切手を貼るスペースを気にしなくてよい
切手を貼る位置を修正する方法
切手を貼った後に、「位置がズレてしまった」「間違った場所に貼ってしまった」 という経験はありませんか?
封筒やはがきを綺麗に仕上げるためにも、切手の貼り位置を間違えた際の適切な修正方法を知っておくことが大切です。
1. 切手を剥がして貼り直す方法
貼り間違えた切手をそのまま無理に剥がすと、破れたり、粘着力が弱まったりする ことがあります。
以下の方法で慎重に剥がしましょう。
(1) すぐに剥がす(貼ってすぐなら簡単)
- 切手を貼って すぐなら、ゆっくりと剥がせば比較的簡単に取れます。
- 端からゆっくりと持ち上げる ように剥がすのがポイント。
(2) 湿らせて剥がす(時間が経ってしまった場合)
時間が経った切手は、粘着が強くなり剥がしにくくなるため、水分を使ってふやかす 方法が有効です。
📌 剥がし方
- 水またはぬるま湯を用意 する(熱湯はNG)
- 綿棒やティッシュに水を含ませ、切手の周囲を軽く湿らせる
- しばらく置き、切手の糊が柔らかくなったらゆっくり剥がす
- 剥がした後は 新しい糊をつけて再貼付 する
💡 注意点
- 水に浸しすぎると 切手のインクが滲む 可能性があるので慎重に
- 速達や書留用の 特殊な切手(バーコード付き)は剥がさないほうが良い
2. 切手の糊が弱くなった場合の貼り直し方法
一度剥がした切手は、粘着力が弱くなる ことが多いため、以下の方法で再び封筒にしっかり貼り付けます。
(1) スティックのりを使う
- 文房具店で売っている スティックのり を薄く塗る
- 水のりは量が多いと紙が波打つ ため注意
(2) 両面テープを使う(小さくカットする)
- 両面テープを切手の裏に薄く貼り、封筒に固定する
- 厚みが出ないように、小さくカットするのがポイント
💡 注意点
- セロハンテープやビニールテープはNG!(郵便局の機械で処理できないことがある)
3. 切手の貼り直しが難しい場合の対処法
切手が破れてしまったり、剥がれた後に再利用が難しくなった場合、以下の方法で対応できます。
(1) 破れた切手はそのまま使える?
- 軽い折れや 端が少し破れた程度なら使用可能(額面が読めることが条件)
- 大きく破れたり、汚れがひどい場合は 郵便局で交換可能(手数料5円/枚)
(2) 新しい切手を上から貼る
- 剥がした切手が使えない場合は、新しい切手を重ねて貼る 方法もあり
- ただし、古い切手が見えないように、しっかりと新しい切手を上に貼る
(3) 郵便局の窓口で相談する
- 切手の状態が不安な場合は、郵便局の窓口で相談するのが確実
- 「この切手は使えますか?」と尋ねると、適切な対応を教えてもらえる
4. 切手を剥がさずに修正する方法
もし、剥がすのが難しい場合は、以下の方法で そのままの状態で修正 することも可能です。
(1) 切手を上から新しく貼る
- 位置が大きくズレていないなら、そのままの上に新しい切手を追加する 方法もあり
- ただし、同じ額面の切手を重ねてしまうと、二重課金になる ので注意
(2) 「切手裏面貼付」のルールを利用する
- どうしても表面に貼るスペースがない場合、封筒の裏面に貼る方法も検討(ただし窓口確認が必要)
まとめ
封筒やはがきに切手を貼るのは簡単なようで、貼る位置や金額を間違えると、郵便物が正しく届かないリスク があります。
特に、切手を貼るスペースがない場合や、複数の切手を使う場合には、工夫が必要 です。
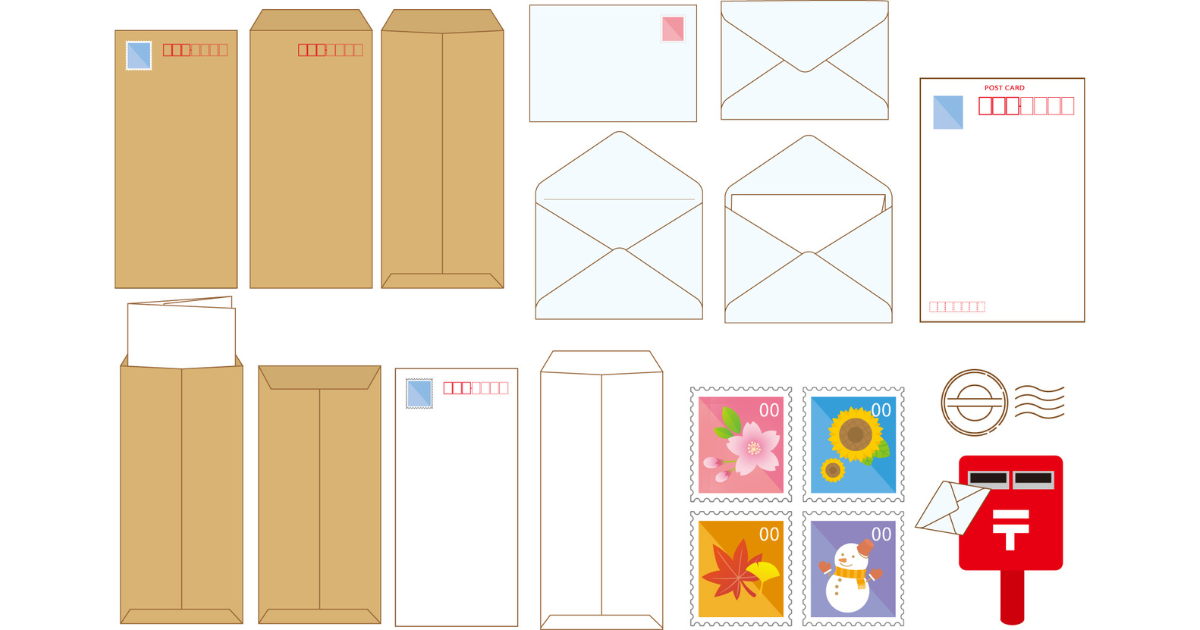
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47f36989.eb2178a2.47f3698a.f653dcf9/?me_id=1411622&item_id=10000266&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdoshisha-marche%2Fcabinet%2Fgorilla%2Fgrf-2401_01test.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
